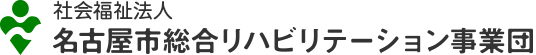学会発表 令和5年度(42件)
- 石黒正樹、鈴木美紗、柏木晴子、福井樹理、小木曽将史、成田ひとみ
障害者支援施設における社会復帰に向けた多職種連携-理学療法士の関わり-
第31回愛知県理学療法学術大会
2023年5月14日
名古屋コンベンションホール&Hybridスタジオ
当施設は、多職種連携に基づく障害福祉サービスにおける自立訓練を提供している。多職種連携による支援を行うことで社会生活能力が向上し、生活の行動範囲が拡大した症例を報告した。理学療法士が多職種と協働することは、手段的日常生活動作の方法や公共交通機関・職場における移動に関する適切な訓練および支援の提供に繋がる。
- 宇井瑞希、中川有花、石黒正樹、渡邉史織、岩田亜由美、尾関諭、鈴木鮎子
社会参加支援に難渋した若年発症脳血管症例
第31回愛知県理学療法学術大会
2023年5月14日
名古屋コンベンションホール&Hybridスタジオ
ひきこもり人口は、全国で100万人以上と推計されている。東京都江戸川区では実態調査が行われ、社会参加支援の難しさが浮き彫りになった。発症前にひきこもりの生活であった若年発症脳血管疾患の入院患者への社会参加支援に難渋した経験を報告した。
- 若泉賢也、生田旭洋、阿部圭佑、岡元信弥、石黒正樹 、稲垣亜紀、堀本佳彦
反復経頭蓋磁気刺激を施行した重度片麻痺患者における歩行能力の経時的変化
第64回日本神経学会学術大会
2023年6月2日
幕張メッセ
脳卒中後遺症による重度片麻痺患者に対し、下肢領域における反復経頭蓋磁気刺激(以下;rTMS)を2クール施行した症例の1年間の歩行能力の経時的変化を検討した。その結果、下肢に重度の麻痺があったが歩行能力が向上し維持された。特にrTMSを行った時期に顕著な向上が認められた。継続した下肢rTMSと理学療法により、経時的な歩行能力向上が得られる可能性がある。
- 古木希春、上村純一、堀本佳彦
体性感覚刺激呈示後の脳活動変動について
第64回日本神経学会学術大会
2023年6月3日
幕張メッセ
体性感覚刺激呈示後の脳活動をMEGを用いて計測した結果、体性感覚関連脳領域間の機能的繋がりは、刺激呈示後1秒で安静時レベルと同等になることが明らかになった。
- 古木希春、渡邉史織、小林直樹
前大脳動脈領域の損傷により更衣動作に困難さが生じた一例
第31回愛知県作業療法学会
2023年6月11日
尾張一宮駅前ビル(i-ビル)(現地+オンデマンド配信)開催
左前大脳動脈梗塞により右上下肢運動麻痺、失語症、強制把握を呈した症例に対し、更衣動作改善のため上肢機能訓練、荷重訓練、両手動作訓練、更衣動作の手順化と模擬動作練習を実施した。段階的に難易度調整をした訓練を行ったことで上肢機能の改善や強制把握の消失に繋がり、円滑な更衣動作が可能となった。
- 塚本倫子
メモ訓練の介入により就労にいたった高次脳機能障害の症例
第31回愛知県作業療法学会
2023年6月11日
尾張一宮駅前ビル(i-ビル)(現地+オンデマンド配信)開催
自己認識低下と記憶障害等の高次脳機能障害を呈する症例に対し、メモ訓練介入の結果、自己認識向上、メモ取り能力改善が見られ、就労につながった症例の報告。
- 一色めぐみ
当障害者支援施設と就労継続支援B型事業所との情報共有が上手くいった症例
第31回愛知県作業療法学会
2023年6月11日
尾張一宮駅前ビル(i-ビル)(現地+オンデマンド配信)開催
当障害者支援施設の作業療法を通じて抽出した問題点を就労移行支援B型事業所へ訪問し、情報共有することにより、利用が可能となった症例報告
- 吉原理美、田中創、川村直希、猪飼大二郎、東久也、妹尾博貴、清水雅裕、渡邉郁人
運転に関する作業療法委員会の紹介
第31回愛知県作業療法学会
2023年6月11日
尾張一宮駅前ビル(i-ビル)(現地+オンデマンド配信)開催
愛知県作業療法士会運転に関する作業療法委員会の紹介を行った。委員である筆者の活動として、なごや高次脳機能障害支援センターと愛知県運転免許試験場との連携および「高次脳機能障害と自動車運転ガイドブック」の活動を報告した。
- 山田和子、広瀬一行、佐藤裕紀、鈴木美代子、石田有紀、林秀幸、諸岡雅美、鈴木朋子
愛知県における失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の成果と課題(続報)2-日帰り温泉での食券・飲料購入手続き支援により、日中活動の拡大を図ることのできた事例
第24回日本言語聴覚学会inえひめ
2023年6月23日
愛媛県県民文化会館
今回、愛知県で初めて趣味・余暇活動において条件付きで派遣が認められ、単独での食事を楽しむことが出来る様になった。失語症が重度になるほど、日常生活場面において意思疎通の困難さを多く抱え、参加場面が限定されやすい。派遣範囲の拡大に向け、支援の必要性を行政に働きかけることが大切であり、失語症のある人のニーズを聞き取る場所が必要である。
- 諸岡雅美、岩井美恵子、林春江、佐藤裕紀、鈴木美代子、山田和子、石田有紀、林秀幸、鈴木朋子
愛知県における失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の成果と課題(続報)3 -自立訓練を利用中に意思疎通支援者派遣を利用開始した事例-
第24回日本言語聴覚学会
2023年6月23日
愛媛県松山市(愛媛県県民文化会館)
失語症者向け意思疎通支援者派遣事業と、高次脳機能障害支援拠点機関で失語症の専門相談支援を担当する筆者が、医療リハと障害福祉サービスにおける自立訓練を利用中に意思疎通支援者派遣を利用開始した事例の、事業・拠点ST、失語症者向け意思疎通支援者、医療リハ担当ST、自立訓練の担当ソーシャルワーカーによる支援経過を報告し、成果と課題を検討した。
- 庵本直矢、渡邉史織、小林直樹、日比野新、竹林崇
亜急性期における脳梗塞後の上肢機能回復と灰白質の構造変化の関連性
第60回日本リハビリテーション医学会学術集会
2023年6月30日
福岡国際会議場
亜急性期における脳梗塞後の上肢機能回復と灰白質の構造変化の関連性を調べた結果、上肢運動麻痺の回復と行動変化の間で異なる灰白質領域の質量変化と関連があった。
- 渡邉史織、小林直樹、庵本直矢
視床梗塞により運動失調を呈した症例のReogo-Jによる上肢運動失調評価の有用性
第60回日本リハビリテーション医学会学術集会
2023年7月2日
福岡国際会議場
視床梗塞により上肢運動失調を呈した症例に対して、上肢機能練習用のロボットデバイスであるReogo-Jを評価として使用した結果、その他神経心理学的検査では反映されなかった運動失調の改善を反映した可能性が示唆された。
- 田中芳則
就学および学校場面における障害児のための支援機器
第37回リハ工学カンファレンスin東京
2023年8月24日
東京大学先端科学技術研究センター
なごや福祉用具プラザでは、これまで就学場面等で必要な支援機器である福祉用具(自助具を含む)を製作改造し、通学、授業(自立活動、体育、音楽)、給食の各場面における障害児の自立を促す支援を行ってきた。今回、通学時の車への移乗用補助具、また授業を受け参加する際に必要な補助具、そして給食時に自分のペースで食べることのできる補助具を提供した事例を報告した。
- 長束晶夫、田中芳則、鈴木光久、内田喜千、横井一輝
競技用マッチング支援の取組
第37回リハ工学カンファレンスin東京
2023年8月26日
東京大学先端科学技術研究センター
障害者のアクティビティやスポーツ参加には様々な用具が使われているが、市販品が合わない場合はフィッティングのために改造が必要である。また1点もので製作したり、作る場合でも高額であるなどの問題がある。このような課題に対して行っている競技用マッチング支援の取組について発表した。
- 岡元信弥、生田旭洋、若泉賢也、阿部圭佑、石黒正樹、稲垣亜紀
上肢領域への低頻度反復性経頭蓋磁気刺激と集中的作業療法の併用療法における歩行能力の経時的変化
第21回日本神経理学療法学会学術大会
2023年9月9日
パシフィコ横浜
上肢領域への低頻度反復性経頭蓋磁気刺激(以下;上肢 rTMS)と集中的作業療法における歩行能力の経時的変化を検討した。上肢機能の改善がみられたが、歩行能力は有意な経時的変化を認めなかった。対象者は下肢機能が高い方が多く、歩行能力改善の天井効果が影響した可能性や対象者がサンプルサイズに至っていないことが考えられた。今後、対象者を増やし、上肢機能と歩行能力との関連を検討する必要がある。
- 田中雅之、古橋友則、青木隆一、堀内恭子、中村透、高戸仁郎
踏切における視覚障害者誘導用設備に関する実証実験
第31回視覚障害リハビリテーション研究発表大会IN金沢
2023年9月10日
金沢商工会議所
踏切における視覚障害者誘導用設備については、その妥当性・安全性については十分検証がされていない。国土交通省の定めるガイドラインの例示と同様の設備が敷設されている大阪の踏切において、実際に視覚障害者に歩いてもらい、踏切の入口・出口の発見や、踏切道の直線歩行が可能かどうかを検証するための実証実験を行った。その結果、現状の設備では、視覚障害者が入口・出口を確実に発見すること、踏切内あるいは外のいずれかにいるかの判断は困難であることが示唆された。
- 西出有輝子、松尾稔、稲葉健太郎
限局した対人関係で年齢を重ねた小児脳損傷者のグループワークー社会的適応のための自信・主体性・協調性を育む試みー
日本心理学会第87回大会
2023年9月16日
神戸国際会議場・神戸国際展示場
小児期以前の脳損傷により、対人関係と社会的経験が著しく限局された女性3名を対象に、自信、主体性、協調性を引き出すことで社会的適応を高めることを目的とし、心理教育的プログラムとレクリエーションからなるグループワークを実施した。
その結果、Vineland2.、行動観察や内省報告から、同年代との関係性の中での経験を重ね、自信を高め主体性や強調性を育むことが、社会生活の質を高める可能性があることが考えられた。
- 佐藤晃、下田誠、松井和夫、中川有花
名古屋市障害者住宅改造補助事業から見る心臓機能障害者の住宅改造
第39回東海北陸理学療法学術大会
2023年9月30日
石川県小松市 サイエンスヒルズこまつ
名古屋市障害者住宅改造補助事業の紹介と本事業を利用した心臓機能障害者の健康状態と生活機能、住宅改造の内容を報告した。心臓機能障害者のNHYA分類は2.から4.と幅があり、年齢や併存疾患も影響していることから、活動制限の程度に応じた住宅改造の提案が重要であると考えられた。
- 石黒正樹、宇井瑞希、萩原康仁、日比野敬明
理学療法科における学術活動および業務改善に関する体制づくり-3年間の取り組みの報告-
第39回東海北陸理学療法学術大会
2023年10月1日
石川県小松市 サイエンスヒルズこまつ
当施設は学術活動を推進しており、理学療法科も積極的に取り組んでいる。また昨今、重複疾患患者の増加や対象領域拡大に伴い、幅広い知識を備え実践レベルを向上することが求められる。そこで我々は学術活動と業務改善、人材育成による実践レベルの向上を目的とした体制づくりを試みている。今回、3年間の活動を振り返り、その有効性を調査した。班活動という体制により、学術活動や業務改善プロセスのナレッジマネジメントを促進することができた。また、外部・内部環境から理想とする在り方を共有することや相互フィードバック等は主体的に学術活動や業務改善に取り組む意欲、自己成長感の向上に繋がることが示唆された。
- 天野佑香、小木曽将史
社会経験が乏しい利用者の意思決定支援
中部ブロック障害者自立訓練事業所協議会・研修会
2023年10月20日
長野県立総合リハビリテーションセンター
特別支援学校卒の社会経験が乏しい利用者が、自分で選択して行動をする機会が少なかったことから意思決定をすることが難しかったケースについて、機能訓練を経て今後の進路を主体的に決定することができた。
- 古木希春、庵本直矢、渡邉史織、上村純一
脳卒中後体性感覚障害を有す症例への触覚・関節位置覚の評価実践報告
第17回日本作業療法研究学会学術大会
2023年10月21日
名古屋大学
脳梗塞により感覚障害を呈した患者に対し、Sensory Assessment Tool (SENSeAssess©)を用いて手指の触覚と手関節の位置感覚について2時点で評価を行った実践報告。
- 福井樹理
生活版ジョブコーチ支援にて家庭復帰に至った高次脳機能障害の1症例
第47回日本高次脳機能障害学会
2023年10月29日
仙台国際センター
入院生活や施設生活では見えにくく,自宅の生活,就学,就労,その他役所手続きなどの社会生活に戻ってから障害が顕在化することが多い高次脳機能障害者に対し、生活版ジョブコーチの考え方を用いて介入し,家族支援を行ったことで家庭復帰に至った症例報告。
- 吉原理美、諸岡雅美、長野友里、佐野恭子、川嶋陽平、永草太紀、稲垣亜紀
頭部外傷後の高次脳機能障害者の実態調査-20年の比較-
第47回日本高次脳機能障害学会学術総会
2023年10月29日
仙台国際センター
1999年より行っていた頭部外傷後の高次脳機能障害者の実態調査について,高次脳機能障害支援モデル事業,支援普及事業を経た20年の変化を調査した.アンケート回収率は58.8%(327/563件)であり,1999年に比べ精神障害者保健福祉手帳の所持状況は10倍以上の増加を認め就労している者の割合が増加した.その一方家庭内外での人間関係トラブルは微増し,就労以外の社会参加におけるさらなる支援拡充が必要と考えられた.
- 沢田梢、有働早紀奈、安井傑、松浦美咲、大島陸、近藤啓太
高次脳機能障害者に対する問題解決プログラムの作成とその効果の検討―予備的研究
第47回日本高次脳機能障害学術総会
2023年10月29日
仙台国際センター
QOLの低下を抱えた高次脳機能障害者に対する心理療法である問題解決療法(以下PST)は、その効果について統一した見解には至っていない。本研究では、高次脳機能障害に対する集団PSTプログラムを作成し、その内容構成と効果について検討した。その結果、問題解決能力を測定するSPSI-R:Sのうち消極的および回避的な問題解決志向において、介入前、介入後よりもフォローアップで有意に得点が低かった。また、参加者のプログラムの評価の平均値(0-5)は3.4から4.3であり、概ね良好な結果が得られた。
- 生田旭洋、石黒正樹、岡元信弥、若泉賢也、石田和人、植木美乃 、稲垣亜紀、堀本佳彦
高頻度反復性経頭蓋磁気刺激(rTMS)と集中的理学療法における歩行能力向上体幹機能の関連性について
第7回日本リハビリテーション医学会秋期学術集会
2023年11月5日
宮崎シーガイアコンベンションセンター
下肢rTMS後の歩行能力向上と体幹機能との関連について検証した報告はないため、下肢rTMSを施行した脳卒中後片麻痺患者14名で検討した。下肢rTMS治療前後の評価について下肢Fugl Meyer Assessment、体幹機能、歩行能力、バランス能力で有意な向上を示した。また歩行能力と体幹機能改善に有意な相関を認め、治療前後の歩行能力に,体幹機能向上が関連していることが判明した。下肢rTMS後の理学療法における歩行能力向上には体幹機能訓練も重要であることが示唆された.
- 柏木晴子、竹味顕子、福井樹理
就労移行支援において、自己認識の変化に焦点を当てることで有効な補償手段の獲得につながった脳損傷の1症例
第57回日本作業療法学会
2023年11月10日~12日
沖縄コンベンションセンター
就労移行支援を利用する脳損傷者に対して,自己認識の程度に応じた補償手段の介入を行ったところ,自己認識の向上とともに有効な補償手段の獲得につながった経験をしたため経過を報告する.症例は50歳代男性,頭部外傷で,受傷6カ月後から当センターの就労移行支援を利用開始した.訓練開始前には,記憶低下の認識が不十分で,補償手段を効果的に活用できていなかった.訓練前半では,忘れのエピソードを共有し,忘れによる影響を実感し始めたところで,補償手段の導入を実施した.訓練後半では,メモの書き方の練習など実用的に補償手段が活用できるように訓練を行った.訓練終了時には,補償手段の必要性を感じる発言があり,自己認識評価SRSIの向上が認められた.
- 田中創、吉原理美、伊藤恵美
運転診断機能を有するドライブレコーダーを用いて安全な運転再開を支援した一例
第57回日本作業療法学会
2023年11月11日
沖縄コンベンションセンター
運転診断機能を有するドライブレコーダーを用いて客観的に運転行動を評価し、対象者が自身の運転行動の問題点を理解するための介入を行い、安全な運転再開を支援した経過を報告した。
- 庵本直矢、渡邉史織、小林直樹、稲垣亜紀、竹林崇
脳梗塞後の麻痺手の使用行動の変化と白質構造変化の関連性
第57回日本作業療法学会
2023年11月11日
沖縄コンベンションセンター
脳梗塞後の麻痺手の行動変化は、皮質脊髄路といった運動に関連する白質線維のみならず、行動学習に関連する白質線維構造の変化と関連している可能性が示された。
- 小林直樹、庵本直矢
拡散テンソル画像を用いて作業療法内容を検討した一例
第57回日本作業療法学会
2023年11月11日
沖縄コンベンションセンター
訓練初期に作業療法評価の他に拡散テンソル画像を用いて予後予測を行い、上肢機能は回復を見込めるが左半側空間無視は残存すると想定した。そのため、左半側空間無視に対してアプローチ、家族指導、居宅訪問をすることとした。その結果、左半側空間無視は残存したが、自宅退院となった。訓練初期から拡散テンソル画像を合わせて予後予測することが重要であると考える。
- 林絵美 、布谷隆史、後藤啓介 、日比野新、間瀬 光人 、飯田 秀博 、福田 哲也 、南光 寿美礼
小脳皮質、小脳髄質、橋における年齢・疾患と脳血流量の関係([15O]GAS-PET 35例の検討結果)
第656回日本脳循環代謝学会学術集会
2023年11月11日
アクロス福岡
【背景】国立循環器病研究センターで開発されたSingle-scan dual-administration (SSDA)法は、PET画像のみから動脈入力関数(AIF)を求めることが可能で、非観血的に脳循環代謝定量画像が作成できる。AIFの部分容積効果とスピルオーバー補正のために、参照領域と参照脳血流値を設定して補正係数の最適化を行うが、その領域は年齢や疾患によらず脳血流変動が小さい部位が望ましい。【目的】小脳皮質と小脳髄質および橋の3種類の脳血流値を求め、年齢・疾患との関係を検討した。対象は、健常5例、血管狭窄・閉塞20例、もやもや病6例、頭部外傷4例の計35例で男性18名、女性17名、年齢は平均55.8歳(24.4~87.3歳)であった。【方法】PMODver3.3を用いて脳血流定量画像とMRI-3DT1画像の自動位置合わせを行った。MRIで解剖学的位置を確認した上3領域を設置し、脳血流値を出力した。脳血流値と年齢との相関(Pearson)、疾患群間の差(Kruskal-Wallis検定)を調べた。【結果】小脳皮質の脳血流は年齢と有意な相関を示した(相関係数0.569 p<0.01)。橋と小脳髄質は年齢相関は認められなかった。小脳皮質と橋の脳血流は疾患群間に有意差が認められた(ともにp<0.01)。一方、小脳髄質は疾患群間で有意差が認められなかった。【考察】大脳皮質の血流は年齢と相関することが報告されており、小脳皮質も同様に加齢の影響を受けたと考える。橋は橋底部の灰白質成分が領域に含まれるが年齢との有意な相関は認められなかった。疾患群別の評価では、脳血管狭窄・閉塞群のうち75%が50歳以上を占め、高齢者の割合が多かったことから、年齢の分布差が結果に影響している可能性があり、今後症例数を増やして再検討が必要である。【結論】白質成分の多い小脳髄質の脳血流は年齢相関や疾患群による有意差が認められなかったことより、AIFの最適化に用いる参照領域として適していると考える。
- 森田勝
リハビリテーション会議終了後も活動範囲が拡大した一症例
第57回日本作業療法学会
2023年11月12日
沖縄コンベンションセンター
先行研究(一般社団法人 全国デイ・ケア協会,2020年3月発行)より,リハビリテーション会議を行うことでLSAが向上したとの報告はあるが,リハ会議終了後の活動範囲の経過について報告したものは皆無である.今回,リハ会議の中で具体的な活動範囲の目標を定め,構成員間の連携によりリハ会議終了から1年経過後も活動範囲がさらに拡大した症例について報告した.
- 市村美生子
「体力測定」の取り組みについて ~現在までの実績とこれからの課題~
第47回 日本障がい者体育・スポーツ研究発表会
2023年11月25日
長野県障がい者福祉センター「サンアップル」
名古屋市障害者スポーツセンターでこれまで実施してきた体力測定の実績の集計、そこから見えてきた課題と今後の展望を発信。参加者層としては、2回目以降の継続参加や、車いす使用者が少なかった。継続に繋がる実施方法や、種目の選定が課題。また、この体力測定を現場でどう評価し、活かしていくのか。他施設とも情報交換をしながらセンター全体の課題として取り組むことが必要。
- 前田麻美
車いすバスケットボール練習日の取り組みについて
第47回 日本障がい者体育・スポーツ研究発表会
2023年11月25日~26日
長野県障がい者福祉センター「サンアップル」
名古屋市障害者スポーツセンターでの実施事業「車いすバスケットボール」の立ち上げから現在までの取り組みについて、センターでは肢体不自由児・者を対象とした事業はあるが団体競技の事業はなかったため団体競技の事業を立ち上げた。立ち上げ時から年度ごとの経過や参加者数の変化、事業に参加したことで参加者の技術面、日常生活や心境の変化についての報告。また、現在実施中の内容についても写真や動画を取り入れながら事例報告。
- 大城徹郎、小木曽将史
失語症者の社会生活力向上における取り組み
全国障害者リハビリテーション研究集会
2023年11月29日
大阪府教育会館たかつガーデン
機能訓練を利用中に意思疎通支援事業を積極的に活用して、失語症を持っていても社会生活の困りごとを解決するための選択肢が増えた事で、単身での生活をより円滑に進める事ができた。
- 田中芳則
オンラインによる難病患者への機器・スイッチ選定適合相談~ICTサポートセンターとしての役割~
全国難病センター研究会第39回研究大会(沖縄)
2023年12月8日
沖縄産業支援センター 中ホール 対面及びリモート開催(Zoomウェビナー)
なごや福祉用具プラザ(以下、プラザ)は、愛知県の障害者社会参加促進事業を受託し、ICTサポートセンターを運営している。これまで遠隔地からの相談もあったが、日程調整の困難さから支援のタイミングを逃さないために訪問ではなく電話やメールでの対応を選択せざるを得ないケースが少なくなかった。しかし近年、コロナ禍で普及が進んだオンラインアプリを使用し、訪問が難しい愛知県内各地域へのサポートのためにICTサポートセンターとして、プラザでも相談業務へのオンイン会議の利活用を始めた。今回、この事例について報告した。
- 吉原理美、中田三砂子、長野友里、佐野恭子、稲垣亜紀
脳損傷後の運転中断者に対する集団プログラムの試み
第9回運転と作業療法研究会学術大会
2024年3月2日
森ノ宮医療大学
脳卒中や脳外傷などの脳損傷は、自動車の安全な運転に支障を及ぼす病気として定められているが,運転中断者への介入報告は極めて少なく,支援は十分であるとは言い難い.今回運転中断を経験している脳損傷者を対象に集団プログラムを実施したところ,有害事象なく高いプログラム満足度が得られた.今後の生活の主な移動手段について運転以外の移動資源によって計画されたことから,本プログラムは運転を中断した生活への準備性が促される可能性が考えられる.
- 古木希春、小林直樹、田中創
タクシー運転手として復職するために運転評価と動作介入を行った一例
第9回運転と作業療法研究会
2024年3月3日
森ノ宮医療大学
脳卒中により左上肢機能障害、軽度の半側空間無視が疑われた症例に対し、タクシー運転手としての復職を目標にして作業療法訓練と自動車運転評価を行った。早期復帰を希望されていたが、症状の改善が認められてから自動車運転評価を行い、業務を想定した環境での訓練は患者の不安感軽減につながったのではないかと考える。
- 一色めぐみ、田中創
高次脳機能障害者に対する公共交通利用獲得に向けての支援
第9回運転と作業療法研究会
2024年3月3日
森ノ宮医療大学
脳出血により高次脳機能障害を呈し,運転を断念した当障害者支援施設利用者が、OTと支援員が連携して公共交通利用獲得に向けた訓練を行ったことで公共交通(電車)利用獲得できたため、それまでの評価や介入についての症例報告
- 佐野明人、鈴木光久、大塚滋、後藤学
腰に乗せて使う揺れる稲穂型歩行支援機
日本機械学会 東海支部 第73期総会・講演会 TEC24
2024年3月5日
大同大学
受動歩行ロボットの揺動慣性に着目した、フィッティングやコストメンテナンスに優位性が見込める新原理の歩行支援機の開発
- 小林直樹、庵本直矢
回復期脳卒中後上肢麻痺患者にAI統合型筋電応答手指リハビリテーションロボットを使用した一例
第9回日本臨床作業療法学会学術大会
2024年3月9日
帝京平成大学 池袋キャンパス
重度上肢麻痺を呈した回復期入院患者に対して日常生活への使用頻度を促した作業療法訓練に合わせて、AI統合型筋電応答手指リハビリテーションロボット(MELTz)を使用した。その結果、握力、ピンチ力で改善を認め、MASが低下し、日常生活でも補助手としての使用が可能となった。作業療法では麻痺手の使用を促し、ロボットでは機能面の改善を促した可能性がある。
- 吉原理美、中田三砂子、長野友里、佐野恭子、稲垣亜紀
障害者支援施設における高次脳機能障害者に対する注意機能グループワークの有用性
第9回日本臨床作業療法学会
2024年3月9日
平成帝京大学
障害者支援施設を利用する高次脳機能障害者に、「注意障害に対する学習カリキュラム」を、試行的に導入した.参加者 4 名全員が 1 回 120 分,全 5 回のプログラムを完了することができ実施可能性を確認した.注意障害に対する自己認識は 4 名とも向上がみられ、特に他者に自身の注意力について説明できるようになることに寄与したことから,自立訓練における本カリキュラムを用いたグループワークは有用である可能性が示唆された.
- 佐藤晃、松井和夫
住宅改造補助事業を利用して浴室環境の改善を提案した腹膜透析・血液透析併用療法患者の一症例
第14回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会
2024年3月17日
朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
名古屋市障害者住宅改造補助事業の紹介と腹膜透析・血液透析併用療法患者に対して、浴室の住宅改造を提案し工事に至ったので報告した。腹膜透析患者の特性である清潔保持と寒さ対策を考慮した上で、住宅改造により得られる効果を利用者と情報共有する必要があると考えられた。