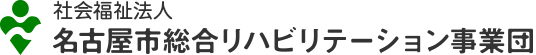情報・資料
視覚支援部門のパンフレット、前年度の実績、よくある質問(QアンドA)、視覚障害の方が利用できる主な制度についてご案内します。
1.視覚支援部門パンフレット
視覚支援課パンフレット(通常版)

視覚支援課パンフレット (ロービジョン版)

2.実績
利用者数(令和6年度)
75名
平均訓練期間
13.4カ月
訓練終了後の進路
一般就労 8名
他施設利用 9名
進学 4名
家庭復帰(家事労働など) 3名
その他(入院や体調不良など) 15名
3.よくある質問(QアンドA)
視覚障害について
(1)見えなくなってしまったらどうやって生活をしていけばいいですか?
眼が不自由になることで、外出や買い物、文字の読み書きやご飯をつくるなど、生活全般において困りごとが出てきます。
そんな中でも、歩行・点字・ICT(パソコンなど)の訓練を受けたり、便利な道具や機器を使ったり、ちょっとした工夫をしてこれまでとやり方を変えることでできないと思っていたことができるようになることはたくさんあります。
一人でできなくても、ヘルパーさんの支援を受けるなど、福祉サービスを活用することで解決できることもあります。そして、それぞれの見え方や生活環境によって解決する手段は異なってきます。
視覚支援課では、そうした様々な解決の手段について情報提供をしながら、一人一人の生活に何が最適な手段か、一緒に考えていきたいと思っています。また、他の利用者さんもたくさん通っています。どんな工夫をして生活をしているか、情報交換することで、新たな手段や生き方に気づくことがあるかもしれません。
(2)視覚障害になっても働けますか?
実際にリハビリセンターの視覚支援課の訓練で、働く上で必要な技能(音声によるPC操作や通勤のための歩行能力)を身につけて社会で働かれている方もいらっしゃいます。また、視覚特別支援学校(盲学校)へ通い、あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格を取得し働いている方もいらっしゃいます。一般の事業所、企業に雇用されることが困難な方は、就労継続支援A型、B型という障害福祉サービスのなかで働ける環境もあります。
(3)身体障害者手帳は取得した方がよいですか? 取得するにはどうしたらよいですか?
身体障害者手帳を持っていると、障害福祉サービスを受けることが出来たり、税金や公共料金の減免や地下鉄やJRなどの公共交通機関での割引を受けることが出来ます。また、生活するうえで便利な道具などについても補助金が下りる場合があります。身体障害者手帳を取得することについて、抵抗感のある方もいらっしゃると思いますが、取得するメリットは多数あると思います。
取得する際は、まず役所の福祉課に行き、相談されると良いと思います。具体的な手続きとしては、役所で「身体障害者診断書(申請用)」をもらい、病院で「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらい、それらの書類を役所に持って行って申請します。
訓練全般について
(4)どのぐらいの視力になったら、訓練を始めたほうがよいですか?
視覚障害によるそれぞれの困りごとを解消するために、訓練は有力な手段のひとつです。ただし、訓練以外で解決できる部分もあると思いますので、個別に相談に乗ったり情報提供を行うことも出来ます。
「歩く時、段を踏み外したり、よくぶつかるようになり怖い」「調理をするとき食器を倒したり、食材をこぼしたりするようになった」など生活に支障をきたすようになったら訓練のはじめ時かもしれません。
それぞれの訓練のはじめ時については、Q(11)(14)(18)をご覧ください。
(5)主治医やケースワーカーから訓練を勧められましたが、本当に訓練が必要ですか?何をしたらいいですか?
まずはご本人が感じておられる困りごとの解決に向けて、適切な方法を考えていきます。訓練により自分でできるようになる解決手段もありますが、ちょっとした道具の使用や福祉サービスの活用で解決することもあるかもしれません。そういった情報提供も併せて行っています。お話を伺いながら一番良い方法を一緒に考えていきます。
(6)不自由ながらも今は何とかやれていますが、今のうちから見えなくなった時に備えたいと思います。視力があるうちから、今後の視力低下を想定した訓練ができますか?
今よりも見えなくなってしまうかもしれないと思うことはとても不安で、そうなる前に準備しておきたい気持ちがあることは当然のことです。
ただ、見えなくなった時の方法で訓練をしても、それを継続していないと忘れてしまったり、感覚が鈍ったりしてしまい、本当に見えなくなってしまった時にせっかくの訓練が活かせないこともあります。
現状の見え方でも、便利な道具を使う事で、見え方の不自由さが軽減できるかもしれません。また、今より見えなくなってしまったとき、どんな方法があるか、どんな道具があるかあらかじめ知っておくことは不安への大きな備えになるでしょう。
実際に視力低下してしまった場合は、再び訓練を受けることも可能です。今は残された視力を上手に活用することを考えてはいかがでしょうか。
(7)身体障害者手帳がないのですが、訓練を受けられますか?
見えづらさによる困りごとがあれば、訓練を受ける事ができます。手帳や障害福祉サービス受給者証を必要としない、「障害者自立支援事業」という形態でも訓練を実施しています。詳細は視覚支援課までお問い合わせください。
(8)一般の企業に就労中なのですが、訓練を受けられますか?
見えづらさによる困りごとがあれば、訓練を受ける事ができます。通勤がこわくなってきた、仕事で使うパソコンの文字が小さくて読めなくなってきたなどの仕事上の困りごとにも対応できます。また、就労中の方のパソコン訓練や歩行訓練の実績があります。ただ、土日祝日の訓練は実施しておりませんので、職場と調整していただいて平日に時間をつくっていただく必要はあります。
(9)訓練の期間はどのくらいかかりますか? 数回で終わりますか?
訓練の期間については、それぞれの方の困りごとや訓練の内容、利用される方の状況によって大きく変わるため、お答えする事が難しいです。各訓練の期間の目安についてはQ(12)(15)(19)をご覧ください。
(10)見学はできますか?
見学を行うことは可能ですが、対応する職員を確保するために、事前に見学を希望される日程を教えていただけると助かります。視覚支援課までお問い合わせください。
また、見学を経て「実際に利用したい」となった場合は、改めて利用相談を受けるという手続きが必要になり、もう一度リハビリセンターに来ていただく必要があります。そのため、利用の可能性のある方は、利用相談の予約を取って、視覚支援課に来ていただいた方が良いかもしれません。
歩行訓練について
(11)いつから歩行訓練をすると良いですか?
電柱や人によくぶつかる、階段がこわくなってきた、電車に乗りづらい、などの移動に関する困りごとが出始めたら訓練をすることを考えてみてもよいのではないでしょうか。
(12)歩行訓練はどのくらいの期間がかかりますか?
見え方の状況や経験、希望する内容や場所により訓練期間がどれくらいかかるかは人それぞれです。白杖の使い方について習得するだけではなく、実際の移動場面でどういった判断をするかという練習も含んでいます。訓練の開始時に希望する内容や現状の見え方について確認したうえで、計画を立てオーダーメイドで訓練を進めていきます。
期間の目安として、全盲に近い見え方で白杖を持ったことがなく外に出ることのできない方の場合、白杖の基本操作から屋内歩行、屋外歩行、道路横断、公共交通の利用、自分で歩きたいところの移動を練習していくまで、半年~1年程度の期間がかかります。目を使ってご自分である程度移動できる方の場合は数回から数か月で終わることもあります。
(13)白杖は持たないといけませんか?
視覚障害の方でも、白杖を持たずに歩いておられる方もいます。ただ、現在の見え方にもよりますが、白杖を持って適切に使う事でより安全に移動できるようになったり、困った際の援助を受けやすくなったりすると思います。まずは、訓練の中で白杖がご自分にとって有効か試してみてはいかがでしょうか。
パソコン訓練(ICT訓練)について
(14)いつからパソコン訓練(ICT訓練)をするとよいですか?
いつから始めるかは、文字の読み書きや情報収集などそれぞれのやりたいことなどが出てきた時や、できると便利だと思った頃が始めるタイミングだと思います。
また、現在お仕事をされている方、これから仕事に就こうと考えている方、盲学校進学をお考えの方は、パソコン技能の習得がほぼ必須になってきていますので、すぐ始めることをお勧めします。
(15)パソコン訓練(ICT訓練)はどのくらいの期間がかかりますか?
これまでの経験や希望する内容などにより、訓練期間がどれくらいかかるかは人それぞれです。最初に希望する内容や今後必要となることを相談し、訓練計画を立ててから進めています。内容によっては数回で終了することもあれば、1年半かかることもあります。また、訓練期間中に生活の状況やご希望の変化に合わせて内容が増えたり、変更することもあります。
おおよその目安として、パソコンの経験が全くない方が、タイピングから文章編集操作、ファイル管理操作、メール・ホームページ閲覧操作など一般的な利用をするための基本操作を習得するのに、概ね1年の訓練が必要とお考えいただければと思います。
(16)どうやってパソコンを使うことができるのですか?
パソコンの画面を読み上げるソフトをインストールすることで、音声を使いながらパソコンを操作することができます。
ソフトは手帳の等級によっては助成金が出て、安く購入することができます。しかし、助成金には上限金額があるので、訓練開始後に自分に必要なソフトは何かを決めてから購入するのが良いと思います。
(17)パソコン訓練を受けるにあたり、あらかじめパソコンを用意しておいた方が良いですか?また、どのようなパソコンを購入すればいいですか?
パソコン訓練は原則視覚支援課にある訓練機で練習をしています。事前に購入しておく必要はありません。パソコンには色々なスタイルや性能があり、どんなものを購入するかはある程度訓練が進み、用途が決まっていく段階から考えていき、利用スタイルに合ったものを選ぶことをお勧めしています。
点字訓練について
(18)いつから点字訓練をするとよいですか?
文字を太く大きく書いたり、ルーペや拡大読書器を用いてもよく読めない、すぐに疲れてしまう、時間がかかり効率的でない等の場合、別の読み書き手段の選択が必要かもしれません。
そうした時に点字訓練を始めると取り組みやすいと思います。また、紙の文字などが見えている段階で訓練をしたとしても、日常的に点字を使わないといざという時に忘れてしまうかもしれません。
(19)点字訓練はどのくらいの期間がかかりますか?
こちらで準備している教材を読み、書きともに終了するのに、概ね1年ぐらいを目安にしています(週1~2回通所の場合)。ただし、進路や目標、障害の状況などにより個人差があるため、それより早く習得される場合もありますし、もっと時間がかかる場合もあります。また、残念ながら最終的に読み書きの実用的な習得までに至らない場合もあります。
(20)仕事や勉強で使うわけではないので、エレベーターや手すりにある簡単な点字だけ読めればいいと思っています。それだけを短期間で訓練を受けることはできますか?
決まった場所の決まった点字を読むことは、何度も繰り返し練習することで読めるようになるかもしれませんが、外出先で出会った、いろんなエレベーターや手すりなどの点字を読む場合、そこに書かれている内容は様々なので結局は一通り読めるようにしておく必要があります。仕事や学習に使う人と比べれば、読み書きのスピードや難しい表記法などの学習の必要がない分、時間の省略ができそうですが、一通り終わらせるにはやはりある程度の訓練期間が必要になります。
4.利用できる主な制度
視覚障害の方がご利用できる福祉制度についてご案内します。
(1)障害福祉サービス
視覚障害の方の外出の手助けをしてくれる同行援護や、自宅での家事のお手伝いをしてくれる家事援助、日中の余暇を過ごす場としてのデイサービスなど、障害福祉サービスを使うことで、充実した生活を過ごされている方や、ステップアップされる方達がいます。もっと詳しく知りたい!という方はお住いの地域の役所の福祉課にお問い合わせください。
(2)障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などになんらかの支障をきたすようになり、障害の程度について一定の基準を満たす場合に受け取ることができる年金です。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。初診日が20歳以前の場合は「障害基礎年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
(3)補装具
補装具とは、身体機能を補完又は代替し、かつ長期的にわたり継続して使用される用具のことです。視覚障害の場合、盲人用安全杖(白杖)、遮光眼鏡、義眼が補装具に当たります。これらの道具を購入する際は、補装具用具費支給制度というものがあり、用具の費用について国から補助が出る制度があります。 国の制度なので全国共通の制度です。
(4)日常生活用具
日常生活用具とは、主に重度の障害者の日常生活の便宜を図るための用具です。用具としては、自立生活支援用具(電磁調理器など)、在宅療養等支援用具(盲人用体温計、体重計など)、情報・意思疎通支援用具(拡大読書器、盲人用時計など)があります。
これらの用具を購入する際には、地方自治体の日常生活用具給付事業というものがあり助成を受けることができます。 用具の内容は、地方自治体により独自に決まっていますので、ある市では対象だが他の市では対象外ということもあります。 (障害者手帳の等級により、補助金が出る用具が変わります。一度買ったらなかなか購入できないものや、制度を1回しか使えないものもあります)
5.スマートサイトあいち
スマートサイトとは
スマートサイトとは視覚障害者および眼科医向けに視覚障害者の支援を行っている施設や団体を紹介しているサイトです。愛知県では愛知県眼科医会が作成しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。