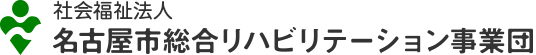高次脳機能障害と自動車運転に関するご相談
高次脳機能障害と自動車運転ガイドブック
高次脳機能障害と自動車運転に関する情報を掲載しています。 下記よりダウンロードしてご活用ください。

高次脳機能障害のある方が、自動車を運転するためには
一般的な流れ
- ご病気などにより、安全な自動車運転が可能な状態かどうか総合的に判断するために、主治医の診断書が必要となる場合があります。
- 診断書を作成するために、乗降動作やハンドル・ペダルを操作する身体機能、注意力などの高次脳機能、シミュレータを用いた反応速度や判断力などを検査することもあります。(検査内容は、個々の心身機能や医療機関によって異なります)
- 評価の結果に基づいて主治医が診断書を作成します。
- 診断書に基づいて公安委員会が最終的な運転の可否判断を行います。
- 判断の結果、運転を控えるよう指示される可能性もあります。その際は、車の運転以外の移動手段を検討する必要があります。
なごや高次脳機能障害支援センターでの支援内容
自動車運転に関するご相談をお受けしています。
運転再開に必要な手続きや、免許更新に関する流れなどご説明します。
専門の相談員(作業療法士)が対応いたします。
平日:9時00分~17時30分
専門の相談員が不在の場合は、後日折り返しのご連絡になることがあります。
相談窓口
電話、窓口、メールでのご相談に対応しています。
どなたでもお気軽にご相談ください。
【電話相談】
052-835-3814(直通)
【窓口相談】
なごや高次脳機能障害支援センター(名古屋市総合リハビリテーションセンター 地下1階)
住所 〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1番地の2
【メール相談】
よくある質問(Q&A)
高次脳機能障害があると、自動車運転にどのような影響があるのですか。
脳の損傷部位によって症状はさまざまですが、注意障害や半側空間無視があると信号を見落としたり、飛び出してくる人や自転車に気付くのが遅れる危険があります。
運転を再開するためには、安全な運転に必要な「認知・予測・判断・操作」に問題がないか確認する必要があります。
必要な手続きをせずに運転再開したらどうなるのですか。
自動車運転免許をお持ちの方が一定の病気などを発症し、適切な手続きがされないまま運転をした場合、法令違反に問われる可能性があります。
免許証の有効期限が過ぎてしまう場合はどうしたらよいのですか。
病気や負傷による入院など、やむを得ない事情がある場合は救済措置があります。
詳しくはご相談ください。
自動車運転に関するイベントのお知らせ
自動車運転に関する講座・相談会を開催しています。
支援者向け研修会を開催します。
過去の研修会での質疑応答集
-
第1回 自動車運転に関する支援者向け研修会 質疑応答集 (PDF 288.6KB)

2022年2月19日に開催された研修会の質疑応答集です。 -
第2回 自動車運転に関する支援者向け研修会 質疑応答集 (PDF 315.9KB)

2023年2月23日に開催された研修会の質疑応答集です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。