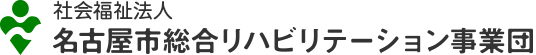情報・資料
障害者雇用の制度・助成金や、ジョブコーチ支援、高次脳機能障害についてご案内します。
1.前年度実績
平均利用期間(令和6年度)
10.5カ月
新規利用者の訓練終了後進路(令和6年度)
| 一般就労 |
新規就労 |
15名 |
|---|---|---|
| 復職 | 22名 | |
| 他施設利用 | 就労継続支援A型 | 5名 |
| 就労継続支援B型 | 2名 | |
| 就労移行支援 | 0名 | |
| その他 | 2名 | |
| その他 | リハセン障害者支援施設 | 1名 |
| 学校 | 0名 | |
| 入院 |
0名 |
|
| その他 |
6名 |
過去の就職先(50音順)
アイカ工業株式会社、アイシン機工株式会社、イオンリテール株式会社、いちい信用金庫、株式会社エスワイシステム、エヌケーシステム株式会社、エム・ユー・ビジネスエイド株式会社、キリックスリース株式会社、株式会社ゲオビジネスサポート、佐久間特殊鋼株式会社、株式会社サンコー、瀬戸信用金庫、第一生命保険株式会社、知多機工株式会社、中京病院、株式会社ティー・エー・エス、東邦ガス株式会社、豊通オフィスサービス株式会社、豊通物流株式会社、株式会社ドン・キホーテ、名古屋市緑市民病院、名古屋昭和建物サービス株式会社、株式会社名古屋中村、日通システム株式会社、日本空調サービス株式会社、日本生命保険相互会社、株式会社パソナハートフル、株式会社パソナヒューマンソリューションズ、株式会社ホンダカーズ東海、株式会社マクシスエンジニアリング、株式会社ミック、学校法人名城大学、株式会社ユニバーサル建設、吉田美装株式会社、リサイクルテック・ジャパン株式会社、リゾートトラスト株式会社、株式会社IEC、MINI、株式会社NTT西日本ルセント、WHP株式会社 など多数
2.利用できる制度(障害者雇用の制度・助成金)
障害者雇用率制度
従業員40人以上の民間企業は、企業全体の従業員数の2.5%の障害者を雇用することが法律で定められています(令和6年4月以降)。雇用率に達していない企業は月50,000円の納付金を国へ納めなければなりません。
ただし、100人以下の規模の事業主は徴収されません。
障害者職場復帰支援助成金
事故や難病の発症などの原因による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成する制度です。一定の要件を満たす必要があります。
特定求職者雇用開発助成金
身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇い入れる事業主に対して賃金の一定率を助成する制度です。
よく活用される制度ですが、一定の要件を満たす必要があります。
トライアル雇用
ハローワークが紹介する障害者を短期間試行的に雇い(トライアル雇用)、常用雇用に移行するためのきっかけを作ります。期間は原則3カ月で、事業主へは奨励金が支払われます。実施にあたっては一定の要件を満たす必要があります。
職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金
【雇用前の支援(実習)】
仕事が出来るか見極める期間になります。事故に備え「災害見舞金制度」があります。
【雇用後の支援】
雇用契約が結ばれるため、「謝金・災害見舞金制度」はなくなりますが、継続的に職業生活をバックアップしていきます。
3.よくある質問
Q:ジョブコーチとは?
A:障害者と一緒に職場に入り、障害者が一人で作業できるよう作業遂行上の支援をしたり、安定した職業生活が送れるように支援します。
Q:名古屋市総合リハビリテーションセンターにもジョブコーチはいますか?
A:現在、数名のジョブコーチを配置しています。
Q:高次脳機能障害とは?
A:私たちの脳は、高性能でデリケートな部品でできたコンピューターにたとえられます。脳は外側を固い頭蓋骨に覆われ、日常生活を送る分には直接傷つきにくくなっています。
ところが、交通事故などで強く頭を打ったり、脳卒中などの病気になることで脳にダメージを受けると、コンピューターの機能が部分的に停止してしまうことがあります。
このようにして生じる症状を総じて「高次脳機能障害」と呼んでいます。大きくは認知障害と社会的行動障害に分けられますが、具体的には以下のようなものです。
具体的な例
- 認知障害
-
- 新しいことが覚えにくくなったり、忘れっぽくなる…「記憶障害」
- うっかりミスや不注意が多くなる…「注意障害」
- 効率的な段取りを立てて行動できなくなる…「遂行機能障害」
- 自分の障害を適切に認識できない…「病識の低下」
- 社会的行動障害
-
- こだわりが強くなったり、自己主張が強くなる…「固執性」
- ささいなことでイライラしたり、怒りっぽくなる…「感情コントロールの障害」
- 欲しいものをがまんできなくなる…「欲求コントロールの障害」
- 相手の気持ちに立って考えられなくなる…「対人技能の拙劣さ」
- できそうなこともすぐに人に頼ってしまったり、子どもっぽくなる…「依存性・退行」
これらの症状は治療やリハビリテーションによってある程度の改善が望めますが、後遺症が残ってしまうこともあります。身体障害を伴わない高次脳機能障害者も多いため、外見からは障害があることが分かりにくく、「見えない障害」といわれることもあります。
こうした高次脳機能障害者は、日常生活を送るうえではそれほど問題がない場合もありますが、判断や臨機応変さを求められる仕事の場面ではミスやトラブルを起こしやすいのです。
たとえば、高次脳機能障害をもつ人に対して「AとBという仕事を明日までにやっておいて」という指示が出たとします。すると、2つの指示のどちらか一方をすっかり忘れてしまったり(記憶障害)、やってもらったのはいいけれどミスだらけであったり(注意障害)、AとBの仕事を一度にやろうとして段取りがうまくいかず、グズグズして期限までに終えられない(遂行機能障害)といったことが起きてしまいます。
また、高次脳機能障害者は物事を関連づけて考えることが苦手になることも多く、これらの失敗を自分の障害のせいだと気付かず(病識の低下)、周囲が悪いと思い込んでしまったり、その状況を判断できないこともあり、職場での人間関係でもトラブルを抱えることがあるのです。
Q:働けますか?
A:本人や周囲が障害を理解し、社会生活を送る上で問題となる行動をできるだけ未然に防ぐように対応することで、問題が最小限にとどまることも分かっています。
事実、自分の障害を認識し、対処法を身につけ、周囲の配慮を受けながら仕事もきちんとしている高次脳機能障害者も大勢います。
Q:障害者手帳の対象になりますか?
A:高次脳機能障害の「診断基準」が策定され、高次脳機能障害と診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になりました。
手帳が交付されれば、就労の際の障害者雇用率制度の対象となります。